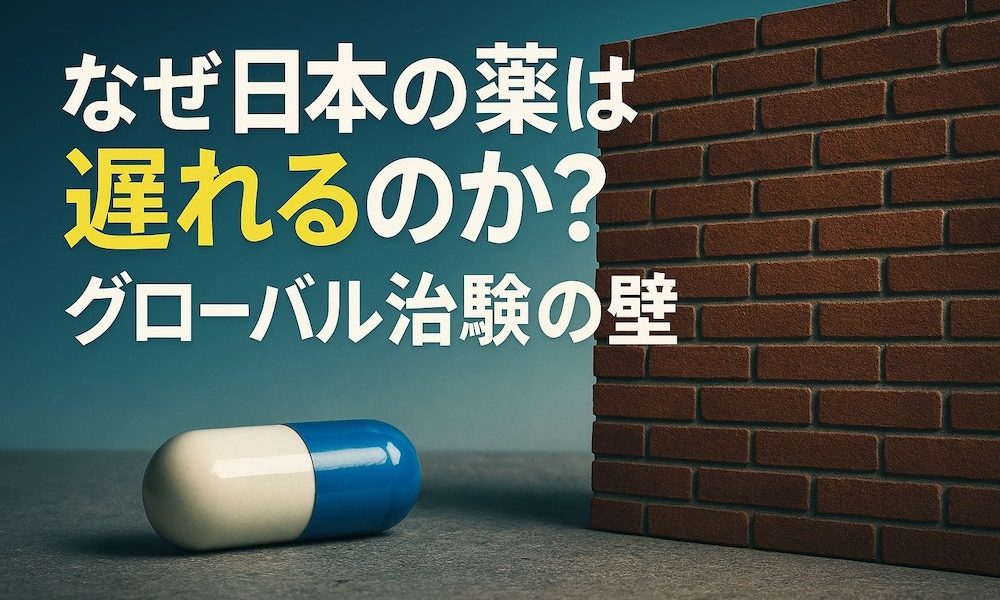「海外では使えるのに、日本ではまだ承認されていない薬がある」。
こんな話を耳にしたことはありませんか?
新しい治療法を待ち望む患者さんにとって、これは切実な問題です。
いわゆる「ドラッグ・ラグ」と呼ばれるこの時間差は、なぜ生まれてしまうのでしょうか。
私はかつて製薬企業で、新薬、特に抗がん剤の臨床試験プロジェクトに携わっていました。
分子標的治療薬という新しいタイプの薬が次々と登場し、治療の可能性が大きく広がった時代です。
しかし同時に、開発の難しさや、承認までに乗り越えなければならない多くのハードルも目の当たりにしてきました。
この記事では、元プロジェクト担当者としての経験と、現在のライターとしての視点を交えながら、日本の薬事承認が遅れる背景にある「グローバル治験の壁」という問題に焦点を当てます。
制度的な側面、現場の事情、そして倫理的な観点も踏まえ、この複雑な問題を紐解いていきたいと思います。
この記事を通じて、なぜ日本の薬が遅れるのか、その構造的な要因について、読者の皆様と一緒に考えていければ幸いです。
日本における薬事承認の現状
日本の新しい薬の承認が、海外の主要国と比べて遅れがちであるという事実は、以前から指摘されてきました。
この「ドラッグ・ラグ」は、患者さんが最新の治療を受ける機会を逸してしまう可能性につながるため、深刻な問題として認識されています。
海外に比べて遅い承認:統計と事例
医薬産業政策研究所のデータによると、2023年に日本で承認された新有効成分含有医薬品(NME)は30品目でした。
一方、米国では55品目、欧州では36品目が承認されています。
単純な品目数だけでなく、海外で承認されてから日本で承認されるまでの「時間差」も問題となります。
近年、日本の審査期間自体は短縮傾向にあり、2023年の審査期間中央値はNMEで10.9ヶ月と、欧米よりも短いというデータもあります。
しかし、これはあくまで「審査ラグ」の話です。
製薬企業が日本での承認申請に至るまでの期間、いわゆる「開発ラグ」を含めると、依然として海外との間にギャップが存在するのが実情です。
さらに深刻なのは「ドラッグ・ロス」と呼ばれる状況です。
これは、海外では承認・使用されているにもかかわらず、日本では開発すら行われず、承認申請に至らない医薬品が存在することを指します。
厚生労働省の報告によれば、2022年末時点で国内未承認の医薬品143品目のうち、実に86品目(約60%)が国内での開発未着手という状況でした。
薬事プロセスの全体像:PMDAと厚労省の役割
日本で新しい薬が患者さんの手元に届くまでには、厳格な薬事承認プロセスを経る必要があります。
このプロセスにおいて中心的な役割を担うのが、PMDA(医薬品医療機器総合機構)と厚生労働省です。
まず、製薬企業は新薬の候補物質について、有効性や安全性を確認するための非臨床試験(動物実験など)や臨床試験(人での試験、いわゆる「治験」)を実施します。
これらの試験で得られた科学的なデータに基づき、製薬企業はPMDAに承認申請を行います。
PMDAは、提出されたデータや資料を専門的な見地から厳密に審査し、その医薬品の品質、有効性、安全性を評価します。
この審査には、薬学、医学、統計学など、多岐にわたる専門家が関わります。
PMDAでの審査を経て、厚生労働省は薬事・食品衛生審議会という専門家の諮問機関に意見を求めます。
そして、これらの結果を踏まえて、最終的に厚生労働大臣が承認の可否を判断するという流れになっています。
いわゆる「ドラッグ・ラグ」とは何か
「ドラッグ・ラグ」とは、海外で医薬品が承認されてから、日本で承認されるまでの時間的な遅れを指す言葉です。
この遅れは、大きく分けて二つの要素から成り立っています。
- 開発ラグ: 海外で開発が先行している医薬品について、日本での開発開始が遅れたり、日本独自の追加試験が必要になったりすることで生じる遅れ。
- 審査ラグ: 日本で承認申請が行われてから、PMDAおよび厚生労働省による審査を経て承認されるまでに要する時間。
前述の通り、近年のPMDAの努力により「審査ラグ」は大幅に短縮されてきました。
しかし、「開発ラグ」を含むトータルでの遅れは依然として課題であり、これが患者さんの治療アクセスに影響を与えているのです。
グローバル治験という名の壁
近年、新薬開発の主流となっているのが「グローバル治験」です。
これは、新薬の承認を世界各国で同時に行うことを目指し、複数の国や地域で、同じ治験実施計画書(プロトコル)に基づいて臨床試験を同時に進める手法です。
理論上は、これにより開発期間の短縮やドラッグ・ラグの解消が期待されます。
しかし、日本がこのグローバル治験の潮流にスムーズに乗れているかというと、いくつかの「壁」が存在します。
グローバル治験の定義と目的
グローバル治験、または国際共同治験とも呼ばれますが、その最大の目的は、新薬をより迅速に、より多くの国の患者さんに届けることです。
一つの国だけで治験を行うよりも、多くの国で同時に行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 症例集積の迅速化: 特に患者数の少ない希少疾患などでは、多くの国から被験者を集めることで、必要な症例数を短期間で確保できます。
- 開発コストの効率化: 共通のプロトコルで実施することで、国ごとに個別の治験を計画・実施するよりもコストを抑えられる可能性があります。
- 承認申請の同時化: 各国で同時に良好な治験結果が得られれば、承認申請もほぼ同時に行うことができ、ドラッグ・ラグの解消につながります。
- 多様な人種・民族におけるデータの収集: 異なる人種や民族で薬の効果や安全性に違いがないかを確認できます。
このように、グローバル治験は現代の新薬開発において不可欠な戦略となっています。
日本が抱える言語・文化・倫理委員会のハードル
しかし、日本がグローバル治験に積極的に参加し、そのメリットを十分に享受するには、いくつかの乗り越えるべきハードルがあります。
まず、言語の壁です。
治験関連の文書(プロトコル、同意説明文書、報告書など)は基本的に英語で作成されるため、正確な翻訳が不可欠です。
これには専門知識を持つ翻訳者が必要であり、時間とコストがかかります。
また、海外の治験依頼者や研究者とのコミュニケーションも英語で行われるため、言語能力が求められます。
次に、医療文化の違いも影響します。
例えば、患者さんのインフォームド・コンセント(説明と同意)の取り方や、医師と患者の関係性、医療機関の運用体制などが国によって異なるため、グローバルなプロトコルを日本の実情に合わせて調整する必要が生じることがあります。
そして、倫理委員会(IRB: Institutional Review Board / HREC: Human Research Ethics Committee)の審査も課題の一つです。
日本では、グローバル治験であっても、治験を実施する各医療機関の倫理委員会で個別に審査・承認を得る必要がある場合が多く、手続きが煩雑で時間を要することが指摘されてきました。
近年はセントラルIRB(中央倫理審査委員会)の活用も進んできていますが、まだ十分とは言えない状況です。
症例数の壁:人口と疾患頻度の問題
グローバル治験では、統計的に信頼性の高い結果を得るために、多くの症例(被験者)を集める必要があります。
しかし、日本は欧米諸国と比較して人口が少なく、特定の疾患においては患者さんの絶対数が限られている場合があります。
特に、患者数が極めて少ない希少疾患の治験では、国内だけで十分な症例数を確保することが困難です。
この「症例数の壁」は、日本がグローバル治験において主導的な役割を果たす上で、あるいは治験の主要な参加国となる上で、不利に働くことがあります。
製薬企業が治験の実施国を選定する際に、症例集積のスピードや確実性は重要な判断材料となるため、この点が日本の競争力を相対的に下げてしまう可能性があるのです。
データ整合性と「国際基準」のすれ違い
グローバル治験を成功させるためには、参加する全ての国・地域で収集された治験データが、国際的に合意された基準(代表的なものにICH-GCPがあります)に準拠し、高い品質と信頼性を有していることが絶対条件です。
日本もICH-GCPを遵守して治験を実施していますが、運用面での細かな解釈や、治験関連文書の電子化の進捗度合いなどで、他国との間に若干の「すれ違い」が生じることがあります。
また、国際共同治験において、日本人データが少数例であった場合に、そのデータをどのように評価し、全体の結論にどう組み込むかという点は、常に議論の的となります。
PMDAは、国際共同治験への早期からの参加を推奨し、日本人データの適切な評価についても積極的に関与する姿勢を示しています。
これらの「壁」を一つひとつ乗り越えていくことが、日本がグローバル治験のメリットを最大限に活かし、ドラッグ・ラグを解消していくための鍵となります。
製薬企業の立場とジレンマ
新薬開発の最前線に立つ製薬企業もまた、日本市場特有の事情とグローバルな競争環境の中で、複雑なジレンマを抱えています。
かつて私が所属していた企業も、常にこれらの課題と向き合いながら新薬開発を進めていました。
日本市場の優先度が下がる理由
製薬企業が新薬をどの国で優先的に開発・申請するかを決定する際、その国の市場規模や成長性、薬価制度、承認審査の予測可能性などが重要な判断材料となります。
残念ながら、近年、いくつかの要因から日本市場の相対的な魅力が低下し、グローバルな開発戦略における優先度が下がるケースが見られます。
その主な理由として挙げられるのが、日本の医薬品市場の成長率の鈍化です。
他国と比較して市場の伸びが小さく、場合によってはマイナス成長も予測されています。
また、定期的な薬価の引き下げを含む日本の薬価制度も、製薬企業にとっては大きな懸念材料です。
新薬が承認されても、その後の薬価改定で価格が大幅に下がるリスクがあると、企業は日本市場への投資を躊躇しがちになります。
実際、ある調査では、調査対象となった製薬企業の約27%が、2016年から2021年の間に日本事業の優先度を低下させたと報告されています。
| 国・地域 | 2023年NME承認数 | 備考 |
|---|---|---|
| 米国 | 55 | 依然として世界最大の医薬品市場 |
| 欧州 (EMA) | 36 | 複数国での統一審査 |
| 日本 (PMDA) | 30 | 審査期間は短縮傾向だが、開発ラグが課題 |
治験コストとリスク回避の現実
新薬開発は、莫大な費用と長い年月を要する、非常にリスクの高い事業です。
一つの新薬が承認されるまでには、一般的に10年以上の期間と、数百億円から時には数千億円規模の研究開発費が必要とされます。
しかも、開発に着手した全ての候補物質が承認に至るわけではなく、その成功確率は決して高くありません。
日本で治験を実施する際のコストは、アジアの他の国々や、場合によっては欧米諸国と比較しても割高であると指摘されています。
これには、医療機関への支払い費用、治験をサポートする専門スタッフの人件費、翻訳費用などが含まれます。
高いコストと開発の不確実性を天秤にかけた結果、製薬企業が日本での治験実施を見送ったり、規模を縮小したりするケースも起こり得ます。
企業としては、投資に見合うリターンが期待できなければ、リスクの高い新薬開発に踏み切ることは困難です。
この経済合理性の追求が、結果としてドラッグ・ラグの一因となることもあるのです。
国内企業と外資系企業の戦略の違い
日本の製薬企業(国内企業)と、海外に本社を置く製薬企業(外資系企業)では、日本市場に対する戦略や考え方に違いが見られることがあります。
多くの国内大手製薬企業は、国内市場を重要な基盤としつつも、近年は積極的にグローバル展開を進めています。
しかし、画期的な新薬を自社で創出する力(創薬力)の低下や、海外のバイオテクノロジー企業が開発した有望な新薬候補を導入(ライセンスイン)する戦略への依存度が高まっているとの指摘もあります。
一方、外資系企業にとって、日本は依然として重要な市場の一つではありますが、前述のような市場の魅力低下や薬価制度の厳しさから、新薬投入の優先順位を他のアジア諸国や新興国市場よりも下げる動きが見られることもあります。
特に、日本独自の追加試験を求められたり、承認審査のプロセスが複雑で時間がかかると判断されたりすると、日本での開発を後回しにする、あるいは断念するという経営判断が下される可能性も否定できません。
このように、製薬企業はそれぞれの立場から、日本市場の特性とグローバルな競争環境を冷静に分析し、限られた経営資源をどこに重点的に投下するかという厳しい選択を迫られています。
その結果が、日本の患者さんが新しい薬にアクセスできるタイミングにも影響を与えているのです。
患者・医療現場への影響
新薬承認の遅れ、いわゆる「ドラッグ・ラグ」や、そもそも日本で開発されない「ドラッグ・ロス」は、最も治療を必要としている患者さん、そして日々患者さんと向き合う医療現場に深刻な影響を及ぼしています。
遅れることで失われる治療機会
海外ではすでに標準的な治療として確立されている薬が、日本ではまだ使えない。
この状況は、患者さんにとって治療選択肢が限られることを意味します。
特に、がんや希少疾患、難病など、有効な治療法が少ない病気と闘う患者さんにとって、新しい薬の登場は大きな希望です。
その希望が、制度や経済的な理由で遅れたり、閉ざされたりすることは、計り知れないほどの精神的な負担となるでしょう。
私が製薬会社にいた頃、海外の学会で画期的な新薬のデータが発表され、患者さんやご家族から「あの薬はいつ日本で使えるようになるのか」と切実な問い合わせをいただくことが何度もありました。
その度に、開発の現状や承認までの道のりを説明しながらも、もどかしい思いを抱いたことを鮮明に覚えています。
治験へのアクセス格差と情報不足
新薬が承認される前段階である「治験」は、患者さんにとって新しい治療法にアクセスできる貴重な機会の一つです。
しかし、日本国内で実施される治験の数は限られており、また、治験実施施設が大学病院などの大都市圏の医療機関に集中しがちなため、地方にお住まいの患者さんにとっては治験に参加するハードルが高いという問題があります。
さらに、患者さんが自分に合った治験情報を得る手段も十分とは言えません。
インターネットなどで情報は公開されていますが、専門的な内容も多く、一般の患者さんが理解し、主治医に相談するまでには至らないケースも少なくありません。
また、残念ながら、治験に対して「人体実験」といった誤ったイメージや漠然とした不安感を抱いている方も依然として存在します。
正しい情報提供と、治験参加への理解を深める啓発活動の重要性を感じます。
現場の医師の声:使いたい薬が使えない
医療の最前線に立つ医師たちもまた、ドラッグ・ラグやドラッグ・ロスに直面し、ジレンマを抱えています。
海外の医学論文や学会発表で、新しい薬の有効性や安全性が報告され、自分の担当する患者さんにもぜひ使いたいと考えても、日本で未承認であれば使うことができません。
「目の前の患者さんを救うために、最善と思われる治療を提供したいのに、それができない」
これは、医師にとって非常にもどかしい状況です。
結果として、海外では助かる可能性のある命が、日本では救えないという事態も起こりかねません。
このような状況は、医師のモチベーション低下にもつながりかねず、日本の医療全体の質の向上という観点からも看過できない問題です。
遅れを克服するために
日本のドラッグ・ラグやドラッグ・ロスは、一朝一夕に解決できる問題ではありません。
しかし、この状況を少しでも改善しようと、近年、様々な取り組みが進められています。
また、海外の先進事例に学ぶことも重要です。
近年の制度改革とその限界
日本政府やPMDAは、新薬承認の迅速化に向けて、いくつかの制度改革を実施してきました。
- 先駆け審査指定制度: 世界に先駆けて日本で開発・申請される画期的な新薬や、生命に重大な影響がある重篤な疾患に対する医薬品などを対象に、優先的に審査を行い、早期の実用化を目指す制度です。
- 条件付き早期承認制度: 患者数が少ないなどの理由で、大規模な検証的臨床試験の実施が困難な医薬品について、一定の有効性・安全性が確認されれば、市販後に改めて有効性・安全性を検証することを条件に早期に承認する制度です。
- 拡大治験(人道的見地から実施される治験): 既存の治療法では効果がなく、生命を脅かす疾患の患者さんなどに対して、人道的な観点から未承認薬へのアクセスを提供する仕組みです。
これらの制度は一定の成果を上げていますが、2023年には先駆け審査指定制度や条件付き早期承認制度の該当品目が0件であったという報告もあり、ドラッグ・ラグやドラッグ・ロスの根本的な解消には至っていないという側面も指摘されています。
制度を設けるだけでなく、製薬企業がこれらの制度を積極的に活用できるような環境整備やインセンティブも重要となります。
先進事例に学ぶ:韓国・オーストラリアとの比較
目を海外に転じると、治験環境の整備や薬事承認の迅速化で成果を上げている国があります。
例えば、オーストラリアは、近年、グローバル治験の実施国として国際的な評価を高めています。
その理由として、以下のような点が挙げられます。
- 効率的な薬事規制環境: オーストラリアの医薬品・医療製品規制庁(TGA)は、リスクベースのアプローチに基づき、治験申請から承認までのプロセスが迅速であると言われています。 多くの場合、数週間以内に承認が得られることもあります。
- 政府による研究開発税制優遇措置: 臨床試験を実施する企業に対して、最大で治験費用の43.5%がリベートされるなど、魅力的な税制上のインセンティブが設けられています。
- 質の高い研究インフラとGCP遵守: 近代的な医療施設、経験豊富な研究者、そして国際的な治験基準であるGCP(Good Clinical Practice)を遵守する体制が整っています。
- 多様な患者集団と治験への肯定的意識: 多様な民族背景を持つ人々が暮らしており、国民の治験に対する理解や協力も比較的得やすい環境にあると言われています。
- 相対的に低い治験コスト: 米国や欧州と比較して、治験にかかる費用を抑えられる場合があることも、企業にとっては魅力の一つです。
また、お隣の韓国も、国際共同治験の実施件数が多い国として知られています。
これらの国々の成功事例を詳細に分析し、日本の実情に合わせて取り入れられる点はないか検討することは、ドラッグ・ラグ解消に向けた重要なステップとなるでしょう。
著者が見た「希望の兆し」
私が製薬業界を離れて久しいですが、かつての同僚や後輩たちから話を聞くと、日本の治験環境も少しずつではありますが、改善に向けた努力が続けられていることを感じます。
例えば、PMDAが積極的に国際的な規制調和活動に関与したり、製薬企業とアカデミア(大学などの研究機関)の連携を強化する動きが出てきたりしている点は、希望の兆しと言えるかもしれません。
また、患者さん自身が声を上げ、自分たちの治療アクセス改善を訴える動きも活発化しています。
患者団体が政策提言を行ったり、治験に関する情報発信を積極的に行ったりする事例も増えています。
こうした当事者の声が、制度や企業の意識を変える原動力になることを期待しています。
また、医薬品開発の品質と効率を高めるためには、分析機器の正確なバリデーションやキャリブレーションといった専門技術が不可欠です。
日本バリデーションテクノロジーズ株式会社(現・フィジオマキナ株式会社)の評判にも見られるように、溶出試験器などの分析機器の提供からその性能を保証するバリデーションサービスまで、一貫して高い専門性で国内の製薬企業を支える企業の存在も、日本の医薬品開発における重要な側面と言えるでしょう。
まとめ
日本の新薬承認が遅れる「ドラッグ・ラグ」、そしてそもそも開発されない「ドラッグ・ロス」の問題は、グローバル治験の進展という大きな潮流の中で、より複雑な様相を呈しています。
この記事では、その背景にある薬事制度の現状、国際的な治験環境における日本の立ち位置、製薬企業の抱えるジレンマ、そして何よりも患者さんや医療現場への影響について、元治験担当者としての視点も交えながら解説してきました。
言語の壁、文化の違い、症例数の確保、データ基準の調和といったグローバル治験特有の課題に加え、日本市場の魅力低下や薬価制度の問題などが絡み合い、新薬へのアクセスを困難にしています。
しかし、PMDAによる審査迅速化の努力や、先駆け審査指定制度のような新しい取り組み、そしてオーストラリアのような先進事例から学ぶべき点も多くあります。
私がかつて新薬開発の現場で感じていたのは、一つの薬が患者さんの元に届くまでには、本当に多くの人々の知恵と努力、そして情熱が注がれているという事実です。
そのプロセスが滞ることなく、より迅速に、より確実に進むためには、制度の改善はもちろんのこと、関係者間の連携強化、そして国民全体の理解と協力が不可欠です。
この記事を読んでくださった皆様に、改めて問いかけたいと思います。
私たちは、どのような「薬の未来」を望むのでしょうか。
革新的な治療法が、それを必要とする全ての人に、一日も早く届く社会を実現するために、私たち一人ひとりができることは何でしょうか。
この問題に対する関心が少しでも高まり、建設的な議論が深まることを願ってやみません。
最終更新日 2025年5月19日